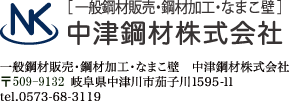なまこ壁の平均単価はいくら?左官職人手作りとタイル工法の違いを解説!
お城の塀や昔の蔵などに施工されていることが多いなまこ壁は、左官職人によって瓦を1枚1枚貼り付け、目次と言われる隙間に白い漆喰を盛って作られていました。
しかし近年、そういった技術を持った左官職人が少なくなったことで、簡易的にできる方法としてタイル貼り工法が注目されています。
そこで今回、左官職人が施工する従来の工法とタイル工法の違いはなにか、なまこ壁の平均単価はどれくらいか、建物に取り入れるメリットはなにかを解説!
これからマイホームを建てようとしている方や蔵などのリノベーションを検討している方は記事を参考にしてみてください。
タイル貼り工法と従来の左官職人工法の違いとは?
従来の工法との違いは、2つあります。
・手作業の工程が多く、手間がかかる。
・人件費や技術料がかかる。
昔ながらのなまこ壁工法を行う場合、瓦と瓦の間のセメントで目地を作るには、均等に作らなければならないことから高度な技術と時間がかかります。そのため、費用も高額になりやすいのです。
一方、タイル貼り工法では、目地もセメントでパーツ化して作ってあることから接着剤で貼り付けるだけのため時間が削減できます。
なまこ壁の平均単価はどれくらい?
従来のなまこ壁の平均単価はタイル貼り工法より1.5倍から2倍程度の費用がかかると言われています。
理由は、左官職人による手作業で施工しており、均等な目地を作るためにはそれなりの時間と高度な技術が必要になるからです。
従来工法 約70,000円~100,000円(1㎡あたり)
タイル貼り工法 約60,000円~80,000円(1㎡あたり)
これらの費用の内訳には、材料費と施工費用、人件費が含まれています。
これらはあくまでも相場となります。最近では、瓦などが高騰しているため従来工法では、費用がより高くなる可能性が考えられます。
また、タイル貼り工法がリーズナブルな価格になっている理由として、瓦と瓦の間のセメントを均等に作る技術が必要ないことが挙げられます。
建物になまこ壁を取り入れるメリットは?
なまこ壁のメリットは、耐久性や耐食性に優れている点です。
蔵などは50年~100年以上前に建てられたものが多く、今なお全国各地で使われています。
つまり、長年雨、風から建物を守れる耐久性は立証されているのです。
大切な建物を守るなまこ壁をぜひ、マイホームの外観や内装のインテリア、蔵のリフォームなどに取り入れて見てください。
まとめ
なまこ壁の従来の工法と比べ、タイル貼り工法は、職人の高度な技術を必要とせず、時間も短縮でき、リーズブルな値段で施工できるのが特徴と言えます。
また、昔ながらの工法で修繕する場合、職人さんは、目地の大きさに合わせてコテを変える必要があり、持っているコテのサイズが合わない場合、自作をしなければなりません。
そのため施工に入る前に1か月程度コテづくりに時間が必要になるケースがありますので、期間も含め取り入れる工法を検討しましょう。